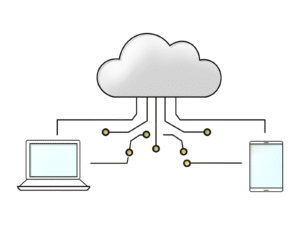機器連携の基本:自動結果入力とSDMSの違い

LIMS(ラボ情報管理システム)を導入するとき、必ずといってよいほど話題になるのが「機器連携」です。
分析装置で得られた結果をシステムに自動で取り込みたい──この要望は多くのラボで共通しています。
しかし「機器連携」と一口に言っても、その中には大きく分けて自動結果入力とSDMS(Scientific Data Management System)という2つの仕組みがあり、しばしば混同されます。
目的や対象データ、導入効果が異なるため、誤解したまま進めると「思っていたのと違う」となりがちです。
この記事では、自社にとって必要なのはどちらの機能なのかを考えるために、「自動結果入力」と「SDMS」の違いをわかりやすく整理します。
ベンダーと話すときの共通言語にもなりますので、ぜひご覧ください。
機器連携とは
まず「機器連携」とは、分析装置などで得られたデータを、LIMSなどの情報管理システムと接続し、自動的に取り込む仕組みを指します。
目的は主に次の3つです。
- 手入力ミス、データ改ざんの防止
- 作業効率の向上
- データの整合性・再現性の確保
しかし、機器連携といっても実現の仕方には大きく2通りあります。
それぞれ「自動結果入力」と「SDMS」に相当します。
これらは明確に異なる機能で、SDMS単独でもシステムとして販売されています。
またLIMSに主に要求されてきたのは自動結果入力の機能でしたが、近年は機能拡張によって両方備えている製品もあります。
ですがどちらかしか備えていないLIMSもありますので、次にそれぞれの目的や機能を詳しく見ていきましょう。
自動結果入力とは

「自動結果入力」とは、分析機器が出力した結果ファイル(csvやtxt等)や、シリアル機器が送信したデータから、必要な情報をLIMSに自動的に取り込む仕組みです。
装置側で計算・出力されたデータをLIMSが読み取り、サンプル番号や分析項目を照合して登録します。
典型的な例としては、次のような装置が挙げられます。
- HPLC、GCなどのクロマトグラフィー分析装置
- 自動滴定装置、分光光度計、天びんなどの定量分析機器
これらの装置から測定後にデータを出力させることで、LIMS側で定義しておいたフォーマットを元に、自動でデータを反映できます。
メリットと導入効果
自動結果入力を導入すると、次のような効果があります。
- 手入力・転記の作業時間が大幅に削減される
- 入力ミスや桁間違いがなくなる
- データ改ざんを予防できる
- 試験結果が即時にLIMSへ反映され、進捗把握が容易になる
また、作業者によるばらつきが減るため、結果報告のスピードと正確性が向上します。
注意点と導入時の課題
一方で、導入にあたってはいくつかの注意点もあります。
- 機器ごとに出力フォーマットが異なるため、それぞれに接続設定が必要になる。
- 機器から出力できないデータは、LIMSに取り込めない場合がある。
- 古い装置は、ネットワーク接続や自動出力が難しいケースもある。
- LIMSが対応していない拡張子や通信規格のデータは、LIMSに取り込めない場合がある。
そのため、導入時には「どの装置のどのデータをLIMSで扱いたいか」を明確にすることが重要です。
現場の分析業務をよく知る担当者の協力が欠かせません。
また、ベンダーにもどのような規格に対応しているか確認しましょう。
SDMSとは
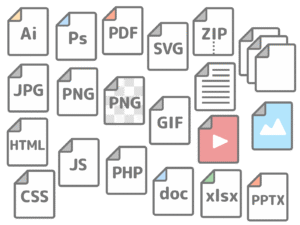
SDMS(Scientific Data Management System)は、分析装置や測定機器が出力する原データファイルそのものを保管・管理するシステムです。
LIMSが「試験結果の管理」を担うのに対し、SDMSは「データの完全性とトレーサビリティを確保する」役割を持ちます。
SDMSでは、各機器PCのデータを定期的に収集し、中央サーバーやNASで一元管理します。
ファイルには作成者・日時・変更履歴などの監査証跡が自動的に付与され、データの改ざん防止や長期保管が可能になります。
また、LIMS上の関連するサンプルや試験と自動的に紐づけられるものもあります。
導入目的と活用シーン
SDMSの主な目的は次のとおりです。
- 原データの一元管理と長期保存
- 監査証跡の自動付与によるデータ完全性(ALCOA+)対応
- ファイルベースデータ(クロマトグラム、画像、スペクトルなど)の検索・再利用性の向上
- 機器故障に対する自動バックアップ
特にGMPやGLPなどの規制下で運用される製薬・化粧品・医薬品原料メーカーでは、規制対応の観点から必須となる場合もあります。
一方で、化学・食品・素材系のラボでは、まずLIMSを中心に結果管理を整え、必要に応じてSDMSを組み合わせる段階的導入が一般的です。
自動結果入力とSDMSの違い

下の表に、両者の違いを整理しました。
| 比較項目 | 自動結果入力 | SDMS |
|---|---|---|
| 主な目的 | 試験結果の自動取込 | 原データファイルの一元管理・監査証跡 |
| データ対象 | 結果値や付随情報そのもの | データファイル |
| 導入効果 | 転記ミス防止、効率化 | データ完全性、トレーサビリティ強化 |
両者は対立関係ではなく、補完関係にあります。
LIMSを中心に据え、必要に応じてSDMSを組み合わせることで、現場の効率化とデータ完全性の両立が可能になります。
「自動結果入力」と「SDMS」は目的が異なるため、どちらを導入すべきか、またはどちらも導入すべきかは、ラボの状況によって変わります。
また、近年のLIMSは「SDMSでファイルを保存しつつ、同時に中身を読み取って結果入力できる」ものもあります。
各社特長がありますので、何ができて何ができないか、ベンダーにしっかりと確認しましょう。
まとめ:データ品質の基盤としての機器連携
機器連携は単なる“便利な機能”ではなく、分析データの品質と信頼性を支える基盤です。
自社の装置構成、試験フロー、求められる品質基準を踏まえたうえで、どのレベルまでの自動化・データ管理が必要かを検討することが重要です。
所有している機器の情報を整理するために、こちらのテンプレートもお使いください。
もし判断に迷う場合は、LIMS導入や機器連携の実績を持つ専門家に相談することで、自社に最も適した構成を短期間で見極めることができます。
当社は豊富な機器連携の経験からアドバイスを提供しておりますので、ご入用の場合はご相談ください。
自動結果入力とSDMSの違いを理解することは、データの信頼性を高める第一歩です。
自社の業務に最も適した仕組みを選び、ムリのない形で“真に活きる機器連携”を実現していきましょう。